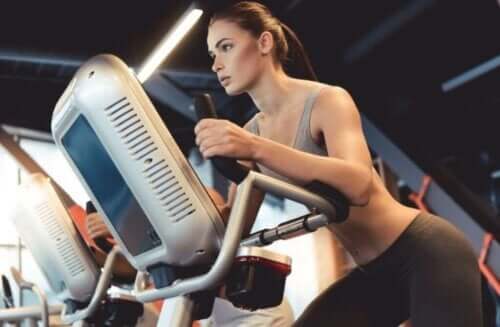オーバートレーニングがもたらすリスクって一体なに?

「多いほど良い」という言葉は、いかなるスポーツにも当てはまりません。運動に関してよくある間違いの一つが、より多くの時間、より多くの日数で運動した方が、より早く、より良い結果を得られるという誤解です。実際はそうではありません。今回は、オーバートレーニングのリスクに関して学んでいきましょう。
オーバートレーニングって何?
毎日数時間の運動をしているアスリートにとって、オーバートレーニングを理解するのは困難かもしれません。しかし、限界を超えて体を酷使することは、後に困難な状況を招くだけなのです。パフォーマンスが低下したり、休んだ後でも心拍数が上がったら、オーバートレーニングの症状が出始めているのかもしれません。
オーバートレーニングのリスクは?
信じないかもしれませんが、前述の症状はほんの一部です。オーバートレーニングは、私たちの肉体的そして精神的な健康に害を及ぼし、そうなると軽減するのは非常に困難です。最も多い問題は以下のとおりです。
けが
度を超えた激しい運動をしたり、限界を超えて長い時間運動したりすると、筋肉や腱は動きを止めてしまいます。これは、時間が経ったり、マッサージをすることで治るので、大した問題に思わないかもしれませんが、前述したように、これは症状の始まりにすぎません。これから悪くなることを体が警告しているのです。

オーバートレーニングによって、肉離れ、筋断裂、そして腱炎のような恒久的な怪我が起きることもあります。また、骨折するケースさえあるのです。
心拍数の増加
前に述べたように、安静時でも心拍数が上がるのは、オーバートレーニングがもたらす弊害の一つで、持続するようであれば治療が必要です。放っておけば、不整脈さらには心停止を引き起こす危険もあります。
体重の減少
ご存じのとおり、筋肉は運動することで、分裂を繰り返して成長していきます。しかし、成長するためには、筋肉を回復させる必要があります。
もし何日にもわたり、数時間の運動を行ったら、この回復プロセスは起こりません。その結果、筋肉は委縮して、体は弱り、筋肉量が増えないために体重も減少するでしょう。さらに、食欲もなくなり、拒食症へと移行する危険もあります。
慢性的な疲労
トレーニングを多く積めば、より抵抗力が増すとは考えないでください。それは全く逆です。オーバートレーニングは限度を超えて体を酷使することになり、慢性疲労を引き起こすことがあります。それにより不眠症となれば、あなたの知的能力、器用さ、協調性は損なわれるでしょう。

ご覧いただいたように、オーバートレーニングは、ドミノ効果で致命的な結果をもたらすこととなり、あなたの仕事のパフォーマンス、人間関係、そして家庭生活にまで影響を及ぼすことになりかねません。
オーバートレーニングに陥ることなく運動をする方法
ジムで過ごす時間が長すぎるとお考えなら、次のヒントを参考に、運動習慣を見直してみましょう。
- 一日に8時間以上の睡眠を取る
- 1週間に最低2日は休む。週末は仕事もジムも休みましょう。休んだからといって、平日の頑張りが無駄になる訳ではありません。それどころか、筋肉は強化されるはずです。休養は運動と同じぐらい重要です。
- 休暇を取りましょう。1年のうちに1か月はトレーニングを忘れて休暇を取りましょう。
- 水をたくさん飲みましょう。体が正常に機能するために、水分補給は重要です。
- 健康的な食生活を。ダイエットの話ではありません。トランス脂肪酸や加工食品は避けて、エネルギー源となる健康的な野菜や生鮮食品を摂るように心がけましょう。
あなたの体は心の持ちようで変わってきます。考え方を変えてみましょう!
食欲不振、心停止、そして慢性疲労といった重大な問題がどれも、オーバートレーニングによって起こり得る最悪な結果である以上、オーバートレーニングを軽視すべきではありません。
「多いほど良い」という言葉は、いかなるスポーツにも当てはまりません。運動に関してよくある間違いの一つが、より多くの時間、より多くの日数で運動した方が、より早く、より良い結果を得られるという誤解です。実際はそうではありません。今回は、オーバートレーニングのリスクに関して学んでいきましょう。
オーバートレーニングって何?
毎日数時間の運動をしているアスリートにとって、オーバートレーニングを理解するのは困難かもしれません。しかし、限界を超えて体を酷使することは、後に困難な状況を招くだけなのです。パフォーマンスが低下したり、休んだ後でも心拍数が上がったら、オーバートレーニングの症状が出始めているのかもしれません。
オーバートレーニングのリスクは?
信じないかもしれませんが、前述の症状はほんの一部です。オーバートレーニングは、私たちの肉体的そして精神的な健康に害を及ぼし、そうなると軽減するのは非常に困難です。最も多い問題は以下のとおりです。
けが
度を超えた激しい運動をしたり、限界を超えて長い時間運動したりすると、筋肉や腱は動きを止めてしまいます。これは、時間が経ったり、マッサージをすることで治るので、大した問題に思わないかもしれませんが、前述したように、これは症状の始まりにすぎません。これから悪くなることを体が警告しているのです。

オーバートレーニングによって、肉離れ、筋断裂、そして腱炎のような恒久的な怪我が起きることもあります。また、骨折するケースさえあるのです。
心拍数の増加
前に述べたように、安静時でも心拍数が上がるのは、オーバートレーニングがもたらす弊害の一つで、持続するようであれば治療が必要です。放っておけば、不整脈さらには心停止を引き起こす危険もあります。
体重の減少
ご存じのとおり、筋肉は運動することで、分裂を繰り返して成長していきます。しかし、成長するためには、筋肉を回復させる必要があります。
もし何日にもわたり、数時間の運動を行ったら、この回復プロセスは起こりません。その結果、筋肉は委縮して、体は弱り、筋肉量が増えないために体重も減少するでしょう。さらに、食欲もなくなり、拒食症へと移行する危険もあります。
慢性的な疲労
トレーニングを多く積めば、より抵抗力が増すとは考えないでください。それは全く逆です。オーバートレーニングは限度を超えて体を酷使することになり、慢性疲労を引き起こすことがあります。それにより不眠症となれば、あなたの知的能力、器用さ、協調性は損なわれるでしょう。

ご覧いただいたように、オーバートレーニングは、ドミノ効果で致命的な結果をもたらすこととなり、あなたの仕事のパフォーマンス、人間関係、そして家庭生活にまで影響を及ぼすことになりかねません。
オーバートレーニングに陥ることなく運動をする方法
ジムで過ごす時間が長すぎるとお考えなら、次のヒントを参考に、運動習慣を見直してみましょう。
- 一日に8時間以上の睡眠を取る
- 1週間に最低2日は休む。週末は仕事もジムも休みましょう。休んだからといって、平日の頑張りが無駄になる訳ではありません。それどころか、筋肉は強化されるはずです。休養は運動と同じぐらい重要です。
- 休暇を取りましょう。1年のうちに1か月はトレーニングを忘れて休暇を取りましょう。
- 水をたくさん飲みましょう。体が正常に機能するために、水分補給は重要です。
- 健康的な食生活を。ダイエットの話ではありません。トランス脂肪酸や加工食品は避けて、エネルギー源となる健康的な野菜や生鮮食品を摂るように心がけましょう。
あなたの体は心の持ちようで変わってきます。考え方を変えてみましょう!
食欲不振、心停止、そして慢性疲労といった重大な問題がどれも、オーバートレーニングによって起こり得る最悪な結果である以上、オーバートレーニングを軽視すべきではありません。
引用された全ての情報源は、品質、信頼性、時代性、および妥当性を確保するために、私たちのチームによって綿密に審査されました。この記事の参考文献は、学術的または科学的に正確で信頼性があると考えられています。
- Bell L, Ruddock A, Maden-Wilkinson T, Hembrough D, Rogerson D. “Is It Overtraining or Just Work Ethic?”: Coaches’ Perceptions of Overtraining in High-Performance Strength Sports. Sports (Basel). 2021 Jun 7;9(6):85.
- Cheng AJ, Jude B, Lanner JT. Intramuscular mechanisms of overtraining. Redox Biol. 2020 Aug;35:101480.
- Halson SL, Jeukendrup AE. Does overtraining exist? An analysis of overreaching and overtraining research. Sports Med. 2004;34(14):967-81.
- Kreher JB. Diagnosis and prevention of overtraining syndrome: an opinion on education strategies. Open Access J Sports Med. 2016 Sep 8;7:115-22.
- Kreher JB, Schwartz JB. Overtraining syndrome: a practical guide. Sports Health. 2012 Mar;4(2):128-38.
このテキストは情報提供のみを目的としており、専門家との相談を代替するものではありません。疑問がある場合は、専門家に相談してください。